■ はじめに
外の世界では、冬になるとコートを羽織り、暖房のきいた部屋でぬくぬくと過ごせます。
しかし塀の中の冬は、そうはいきません。
暖房設備が限られるうえに、換気も制限されやすい――。
寒さと感染症のダブルパンチに、受刑者も職員も神経をすり減らす季節です。
今回は、「刑務所の冬」と「寒さ・感染症対策」について、知られざる実態を見ていきましょう。
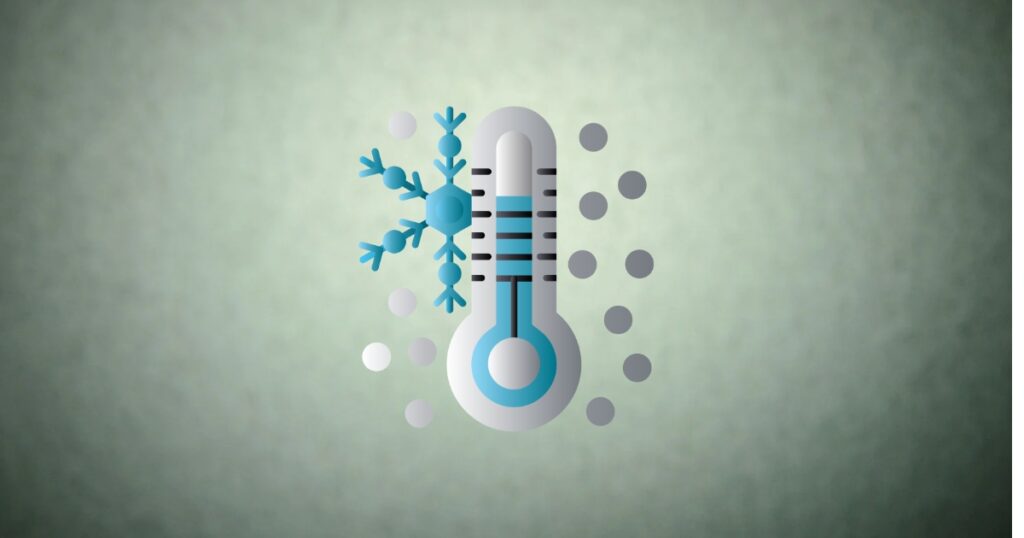
■ 暖房は“特別待遇”ではない
刑務所の房内にエアコンがあると思う人は少なくありません。
しかし実際には、ほとんどの房に個別暖房は設置されていません。
冬場の暖房は石油ストーブや温風ヒーターが限られた時間だけ稼働し、
全館暖房とは程遠い状況です。
服装も支給品が基本で、厚手の下着やジャンパーは数が限られています。
多くの受刑者は、毛布を何枚も重ねて体温を逃がさない工夫をしています。
寒さの厳しい地域の刑務所では、夜間の室温が一桁台になることも珍しくありません。
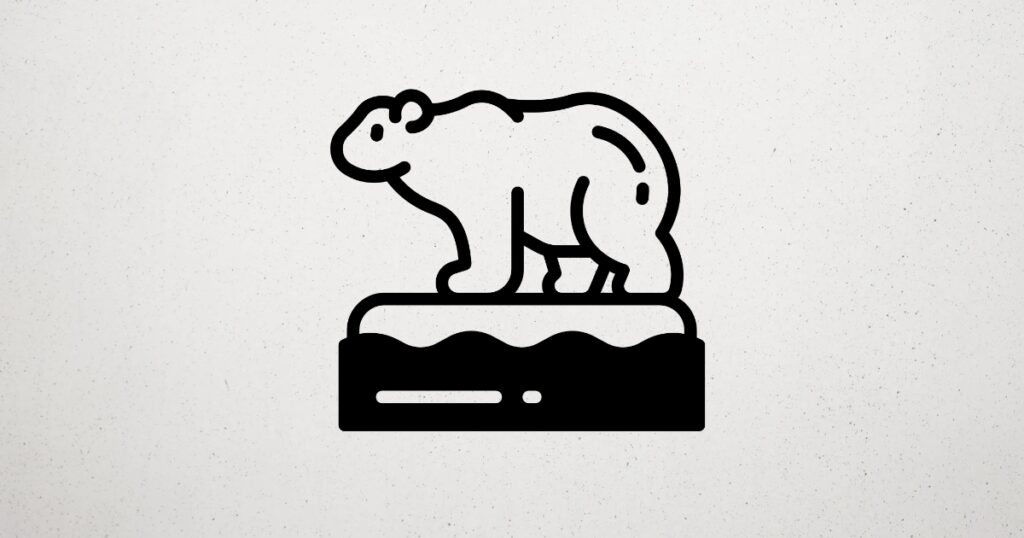
■ 換気と寒気の狭間で
冬の刑務所で難しいのは「換気のバランス」です。
窓を開ければ冷気が入り、閉めれば空気がこもる。
しかし感染症対策の観点からは、定期的な換気が欠かせません。
特に、インフルエンザや新型コロナの再流行期には、
看守が巡回しながら窓を一時的に開閉し、空気の流れを調整します。
受刑者の体調を確認しつつ、咳や発熱の兆候があれば
即座に医務課へ報告し、隔離処置が行われます。
外から見れば単純な「窓の開け閉め」ですが、
それは命を守る行為でもあり、塀の中では綿密なルールのもとで行われているのです。
■ 作業場での防寒対策 ― “動いて温める”知恵
作業場の暖房設備も限られているため、
受刑者たちは身体を動かすことで体温を上げる工夫をしています。
重作業では汗をかき、軽作業では冷えが厳しくなる。
このバランスを取るのが難しく、職員も休憩ごとに水分・体調をチェックしています。
冬季には、手袋の支給や防寒靴下の着用が認められる場合もあります。
しかし安全面の理由から作業中の着込みすぎは禁止。
まさに「寒さと規律のはざまでの作業」と言えるでしょう。

■ 感染症との戦い ― 予防接種と隔離措置
刑務所内では、インフルエンザの集団感染が毎年のように課題になります。
風邪一つでも、閉鎖空間では一気に広がるため、
医務課は早期のワクチン接種を呼びかけ、症状のある受刑者を隔離する体制を整えています。
独房や特別居室が臨時の隔離室に転用されることもあり、
感染者が出た棟では面会や作業を一時停止して対応することも。
この徹底ぶりは外部の病院顔負けで、
「閉ざされた空間ゆえに、感染を止める努力もまた徹底している」と言えるでしょう。
■ 職員の苦労と現場の知恵
職員にとっても冬は厳しい季節です。
屋外警備や夜間巡回は氷点下でも続き、
「寒さを我慢してでも体調を崩すわけにはいかない」というプレッシャーと戦っています。
彼らは勤務前にポケットカイロを複数持ち、
巡回ルートを短縮して冷気の中での滞在時間を減らすなど、
“現場流の寒さ対策”を編み出しています。
寒さに震える受刑者の姿を見て、
毛布の追加支給を提案するなど、
人としての思いやりが垣間見える場面もあります。

■ まとめ ― “暖かさ”とは温度だけではない
刑務所の冬は、設備の寒さ以上に「孤独の寒さ」が身に染みる季節でもあります。
けれど、看守の一言や、同房者の助け合いが、
凍える夜をほんの少し温かくしてくれる――。
塀の中にも、人のぬくもりは確かにあります。
そのぬくもりこそ、外の世界が忘れがちな“本当の防寒対策”なのかもしれません。
🪶筆者メモ
冬の塀の中を知ると、「当たり前の暖かさ」がどれほど贅沢かに気づかされます。
毛布一枚のありがたみ、湯飲みから立ちのぼる湯気の尊さ。
人の心もまた、冷たくも温かくもなれる――
そのことを、刑務所の冬は静かに教えてくれます。




コメント