私たちが地震に備えるとき、真っ先に思い浮かべるのは「避難」ではないでしょうか。
しかし――刑務所の中では、そう簡単にはいきません。
鍵のかかった部屋、鉄格子、数百人単位の受刑者。
地震が起きても、「すぐに外へ逃げる」という行動ができない空間なのです。
では、塀の中の人々はどのように命を守っているのでしょうか。
今回は、知られざる「刑務所の防災体制」を見ていきましょう。

- 鍵を開けるにも手順がある ― “即時避難できない”現実
一般社会では、地震が起きたら「ドアを開けて避難口を確保」と教えられます。
しかし刑務所では、どの扉にも必ず鍵がかかっています。
刑務官が合図を出さない限り、受刑者は自分で逃げることができません。
地震発生時、まず刑務官たちは
- 被害状況の確認
- 鍵の所在と避難経路の確保
- 各房の点呼・解錠手順
これらを一斉に判断・行動しなければなりません。
そのため、「開ける」までの数分間が命を分けることもあるのです。
実際、阪神・淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)でも、
各地の刑務所では「倒壊は免れたが、避難まで時間がかかった」事例が報告されています。
- 耐震化が進む刑務所 ― 古い建物から新しい構造へ
現在、全国の刑務所は順次耐震補強や新庁舎建設が進められています。
特に、古い煉瓦造や鉄筋コンクリートの施設では、耐震基準を満たすよう改修を実施。
- 壁や天井の補強
- 落下物防止の棚固定
- 緊急用発電機や貯水タンクの設置
刑務所は「公共施設」でありながら、外部避難が難しいため、
“中で完結できる防災”が求められるのです。
一方で、老朽化した地方施設などは改修が追いつかず、
一部では「避難経路の確保が課題」とされています。

- 鍵管理と避難訓練 ― “安全”と“迅速”の両立
刑務所での防災訓練は、一般の避難訓練とはまったく異なります。
目的は「逃がさないこと」ではなく、“安全に避難させること”と“秩序を守ること”の両立です。
刑務官たちは、
- 鍵の所在・開錠手順を全職員で共有
- 一度に全員を出さず、棟ごとに避難誘導
- 混乱や暴動を防ぐため、指示系統を一本化
といった訓練を定期的に実施しています。
受刑者側も、防災放送を通じて指示を聞き、静かに待機するよう教育されています。
つまり、刑務所の防災とは――
「動かない勇気」と「守る秩序」が命を支える」世界なのです。
- 避難先も“塀の中” ― 限られた安全地帯
地震で建物が損壊した場合でも、受刑者を外に出すことはほとんどありません。
多くの刑務所では、構内に「避難広場」や「運動場」を設けており、そこが一時避難所となります。
外部への避難は、
- 塀が崩壊した場合
- 火災・爆発などで敷地内が危険な場合
といった、極めて例外的なケースに限られます。
そのため、刑務所内の避難スペースは広く、
簡易トイレ・飲料水・毛布などの備蓄も一般施設より多めに確保されています。
- 職員の家族も被災者 ― 二重の緊張
地震が起きたとき、刑務官自身も被災者です。
家族の安否が分からなくても、まず優先されるのは「受刑者の安全確保」。
それが職務であり、使命でもあります。
しかし、職員が不足すれば警備が手薄になり、
混乱を招くリスクもあるため、勤務体制の維持と家族支援が重要な課題とされています。
東日本大震災では、
一部の刑務官が「家族の避難よりも施設に残った」と語る証言もあり、
その責任の重さが改めて注目されました。
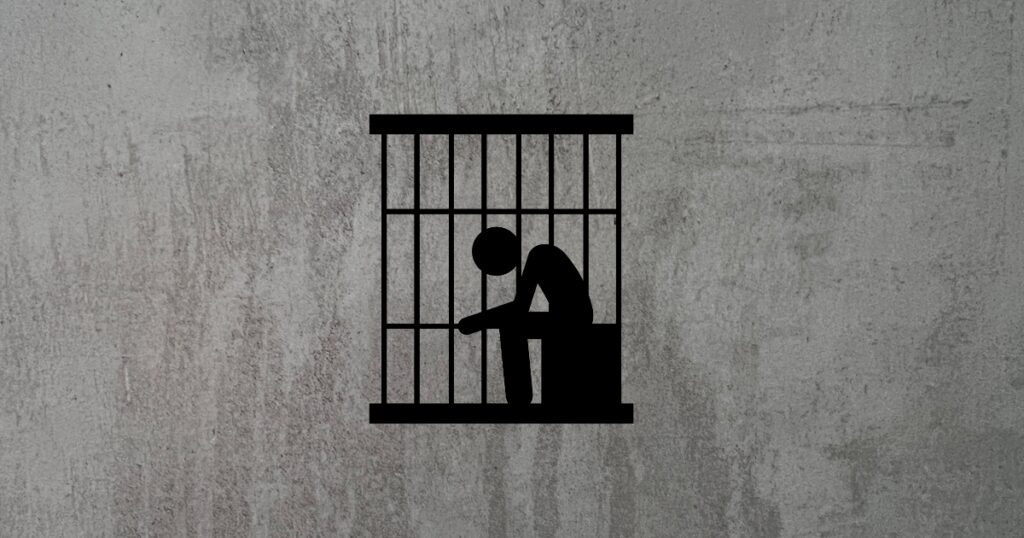
- “もしも”の時、秩序を守るのは人の信頼
塀の中では、逃げることも助けを呼ぶことも自由ではありません。
そんな環境で命を守るために必要なのは、
設備でもマニュアルでもなく――人への信頼です。
「職員を信じて待つ」
「受刑者を信じて守る」
その両方があってこそ、地震の混乱を最小限に抑えることができます。
まとめ:動けない場所だからこそ、動ける準備を
地震大国・日本において、刑務所の防災は社会全体の縮図とも言えます。
自由が制限された空間で、いかに人を守るか。
それは、私たちが日常で何を大切にするかを映し出す鏡でもあります。
次に大きな地震が来たとき――
塀の内側でも、外の社会でも、命を守るために
「信頼」と「秩序」が支えになることを、忘れたくありません。
«次回予告:「夏の塀の中は灼熱地獄? ― 刑務所の熱中症対策」»




コメント