
20代の頃、叔父の大工仕事を手伝っていた時期がある。
その現場は、松山刑務所のすぐ隣にあった。
休憩時間になると、作業員たちの話題は決まって「この前の脱獄未遂事件」だった。
刑務官の車のタイヤ4本が一晩でなくなった、というのだ。
ブロックをジャッキ代わりに敷き、車体ごと持ち上げられていた──誰がどうやってそんな芸当を?と皆が首をかしげていた。
あの日、木槌の音とともに遠くから響いてきたのは、金属扉の重い開閉音だった。
風に乗って漂ってくるのは、木工所から流れる木屑の匂い。
刑務所の敷地からは、作業服姿の人々が静かに列をなし、夏の日差しに白く光る。
それを見て、私は「塀のない刑務所」という言葉の意味を初めて肌で感じた。
🏠 松山刑務所という“開かれた環境”
松山刑務所は、全国でも珍しい「塀のない刑務所」として知られている。
ここには、比較的軽微な犯罪を犯した人々が収容されており、
高いコンクリート塀の代わりに、緩やかなフェンスと地元の緑に囲まれている。
近隣の住民にとっても刑務所は“遠い存在”ではなく、
秋には「矯正展」と呼ばれるイベントで受刑者の作業製品──木工品や革細工──が販売される。
市民が刑務所の敷地に足を運び、商品を手に取る。
そこには、確かに**「社会と刑務所のあいだ」**が存在している。

⚒️ 自由と信頼のあいだにあるリスク
受刑者の中でも、特に模範的な態度を示した者には、
今治造船など外部企業での作業が許されることがある。
それは、再社会化への第一歩でもあり、社会の信頼を取り戻すための機会でもある。
だが、自由には常にリスクが伴う。
かつて、この制度を利用して作業中に脱走を試みた受刑者がいた。
今治から海を泳いで広島方面へ渡ろうとしたという。
結果的に確保されたが、この行為は刑法上の「逃走罪」にあたり、刑期の延長や懲罰房での厳しい処遇が科される。
松山刑務所では、脱走未遂そのものが「重大な規律違反」として記録され、
それまで積み上げた信頼や優遇措置はすべて取り消される。
🌳 塀のない刑務所が映す“社会との接点”
塀のない刑務所とはいえ、その内側と外側の間には、目に見えない境界線がある。
風が吹けば、刑務所の中の音もこちらに届く。
しかし、その風が越えることのできない壁が、確かに存在している。
街の人々にとっては見慣れた風景かもしれない。
だが、そこにいる人々にとっては、自由と更生のはざまに立たされた時間そのものだ。
刑務所が地域に溶け込みながらも、常に緊張感を孕んでいるのは、
この「見えない塀」が社会の一部として呼吸しているからだろう。
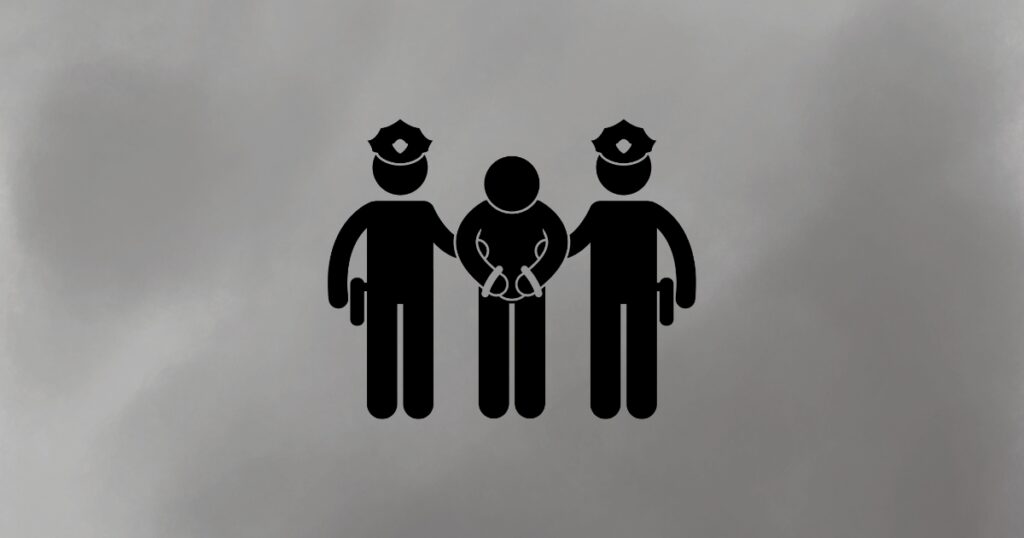
⚖️ 脱獄事件がもたらす影響
脱獄や脱走未遂は、単なる規律違反ではなく、新たな犯罪として扱われる。
刑法第97条では、「拘禁を免れる目的で逃走した者は、1年以下の懲役」と定められている。
さらに、その行為によって警備体制が強化され、他の受刑者の日常にも影響を及ぼす。
つまり、ひとりの行動が、刑務所全体の「信頼度」を下げてしまう。
「塀のない刑務所」という形が成り立つのは、社会と受刑者の双方の信頼があるからこそ。
そのバランスを崩す行為は、本人だけでなく全員の自由を奪ってしまうことになるのだ。

✏️ 補充裁判員としての視点
私が裁判員として見た「刑に服する」という言葉の重みは、
この松山刑務所の風景と重なって見える。
判決文の中では数行で済まされる「懲役〇年」という言葉も、
現実にはこのような日々の積み重ねであり、
その中には人間の葛藤と再生への努力が確かに存在している。
塀の向こうに見えるのは、単なる“刑の場”ではない。
社会の一部として、そこに息づくもうひとつの「現実」だ。
💡 まとめ:松山刑務所が教える“自由の責任”
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 日本で数少ない塀のない刑務所 |
| 作業内容 | 木工・革細工・外部企業での作業など |
| 利点 | 信頼を積めば外部作業の機会が得られる |
| リスク | 脱走=刑法上の犯罪、懲罰・刑期延長の可能性 |
| 教訓 | 自由には必ず責任が伴う |
🕊️ 次回予告
次回は「刑務所作業の日常──受刑者が作る“あの製品”の裏側」について。
私たちの身近にある“矯正製品”が、どんな環境から生まれているのかを掘り下げてみます。




コメント