裁判はいよいよ後半戦へ
この裁判もいよいよ後半戦に差し掛かりました。
今回の中心となるのは、被告人に対する質問――いわゆる「被告人質問」です。
ここでは検察官と弁護人、それぞれが被告人に直接質問を投げかけ、事件の真相に迫ろうとします。

入れ知恵に踊らされる被告人
被告人はこれまでの審理の中で、事件後も自ら考えることなく、同僚からのいい加減な入れ知恵に従い、次々と矛盾する証言を繰り返してきました。
検察側もそのたびに頭を抱え、弁護人も「もう擁護しきれない」といった様子。
まるで幼い子供のように自己保身ばかりを考え、罪の重さを理解していない――そんな印象を受けました。
彼にとって「考える」という行為は、他人の言葉をなぞることに等しいのかもしれません。

刺したあとも救助せず、SNSに投稿
事件当日、被告人は被害者を刺した後も救助をせず、ただオロオロするばかりでした。
同僚に助けを求めるも、周囲の仲間も真剣に対応することはなく、結果として被害者は自力で社員寮を出て、公園まで逃げ、通りかかった地元住民が119番通報。
救急車で病院に搬送されたことで命を取り留めました。
一方、被告人はというと――刺した包丁の血を洗い流し、証拠隠滅を図ったあとFacebookに「同僚を刺した」と母親へ投稿。
SNS上で事件を報告するという、現実離れした行動を取っていたのです。
この場面を聞いたとき、法廷内に小さなどよめきが起こりました。
「そこに人間の心はあるのか?」という空気が漂っていたように感じます。
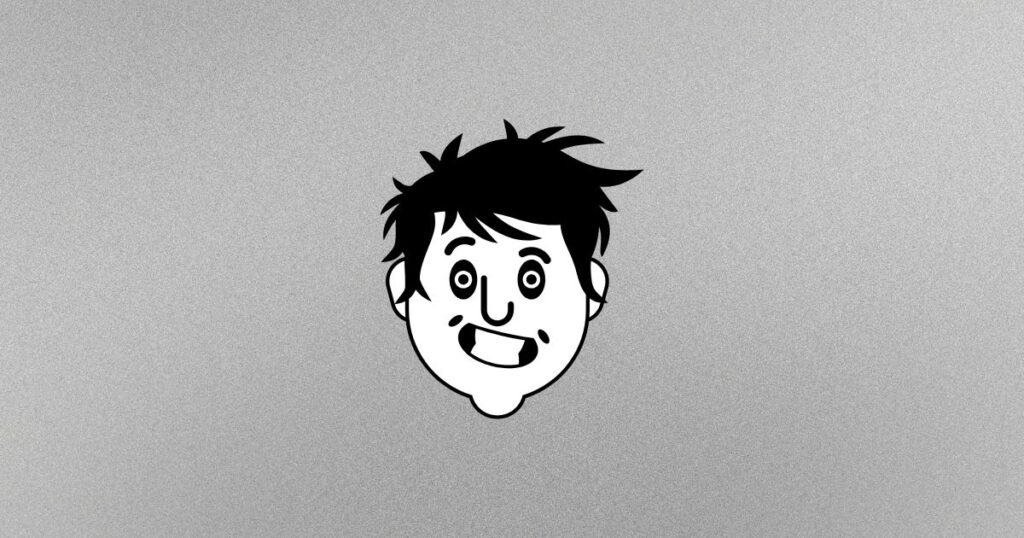
無関心という名の文化
さらに印象的だったのは、彼とその仲間たちの“日常の感覚”でした。
彼らにとっては、諍いが起こっても仲裁せず、見て見ぬふりをするのが普通。
誰かが血を流すほどの事態になって、ようやく「落ち着け」と止めに入る――そんな世界が当たり前のようです。
しかし、負傷した仲間を助けることはしない。
助けを呼ぶことも、責任を共有することもない。
これが、**彼らの“普通の社会常識”**なのだとすれば、日本人の感覚からすると大きな断絶を感じざるを得ません。
人としての「助け合い」や「思いやり」が欠落しているように見えるのです。

法廷で浮き彫りになる文化の壁
この一連のやり取りを通して感じたのは、単なる殺人未遂事件ではなく、文化的背景と倫理観の衝突という構図です。
日本社会では、他人の痛みに共感し、状況を察して助け合うという価値観が根付いています。
一方で、被告人のように「自分の責任を他人任せにし、結果を受け止めない」という姿勢が、いかに危ういものかを法廷は示していました。
まとめ
この日の法廷は、被告人の幼稚さと無関心さが際立った一日でした。
人を刺しておきながら、救助もせず、SNSに書き込む――まるで現実を理解していないような姿。
それでも、弁護人は冷静に「なぜ彼がそうなったのか」を掘り下げようと努力していました。
しかし、文化の違いと人間の本質が絡み合うこの事件。
その根底には、“人の痛みを感じ取れない社会”という、もっと大きな問題が潜んでいるように思えてなりません。




コメント