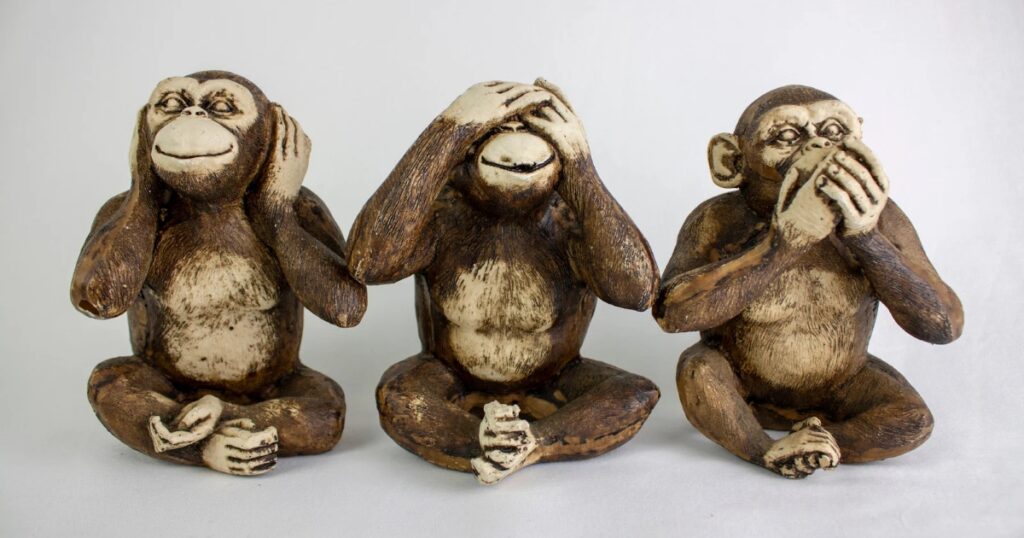
目撃者の証言は「見ざる言わざる聞かざる」
今回の法廷では、目撃者による証言と法医学者による専門的な解説が行われました。
最初に登場した目撃者は、事件当時の現場を見ていた人物……のはずでしたが、実際には「見ていない」「覚えていない」「分からない」を繰り返すばかり。
まるで「見ざる・言わざる・聞かざる」を徹底的にインプットされたかのような受け答えで、検察官の質問にもまともに答えず、法廷の空気は次第に重くなっていきました。
被告人や被害者のように感情的な証言でもなく、かといって事実を明確にするわけでもない──この目撃者の存在は、ある意味で一番“強者”だったのかもしれません。

法医学者が語る「包丁の軌道」
午後からは、愛媛大学医学部の法医学者の先生が証人として登場。
冷静な語り口で、事件の「見えなかった部分」を医学的に紐解いていきました。
被告人は「包丁を下に向けて軽く持ち、背中を押したら刺さってしまった」と主張していましたが、法医学的な事実はまるで違いました。
包丁は右肩甲骨の下から↙方向へ進み、背骨の突起を骨折させながら斜めに進行。左肋骨の一番下で止まったとのこと。
軽く押しただけでこんな軌道を描く刃物……もはや「スタンド使い」かと思うほどの不自然さでした。
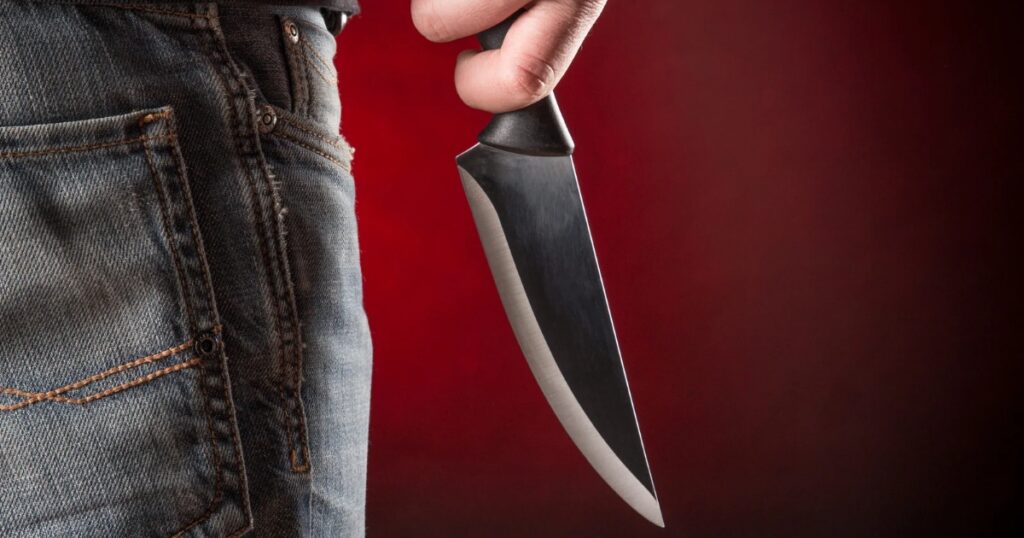
血液量4分の1の喪失と“優しい包丁”の殺意
さらに衝撃的だったのは、被害者が失った血液量。
全体の4分の1を失っており、出血量としては命に関わるレベルです。
法医学者によれば、傷口から流れた血液が周辺臓器に混じることで、少量でもショック死を引き起こすことがあるとのこと。
「優しい包丁」でも、時として強い殺意を宿し、人を死に至らしめる──そんな現実が、冷静な専門家の言葉によって浮き彫りになりました。

日本社会と文化のズレに感じた違和感
この証言を聞きながら、私は一つの違和感を覚えました。
被告人も被害者も外国人研修生であり、日本社会の文化や地域特性を十分に理解していないまま、地方という閉鎖的な社会に飛び込んでいます。
日本には「郷に入れば郷に従え」という言葉がありますが、彼らの行動には周囲への観察や協調という姿勢が著しく欠けているように見えました。
特に地方では人々の目が厳しく、日常の小さな行動が注目されます。
にもかかわらず、自国の感覚をそのまま持ち込み、自己中心的な行動を続けた結果が、事件の背景にも潜んでいるように思えたのです。
企業と自治体への教訓
この事件は、単なる刺傷事件ではありません。
外国人研修生を受け入れる企業や自治体にとって、地域社会への適応や文化理解をどう支援するかという大きな課題を突きつけています。
労働力として迎え入れるだけではなく、その土地に根付くための教育と環境づくりが求められていると強く感じました。
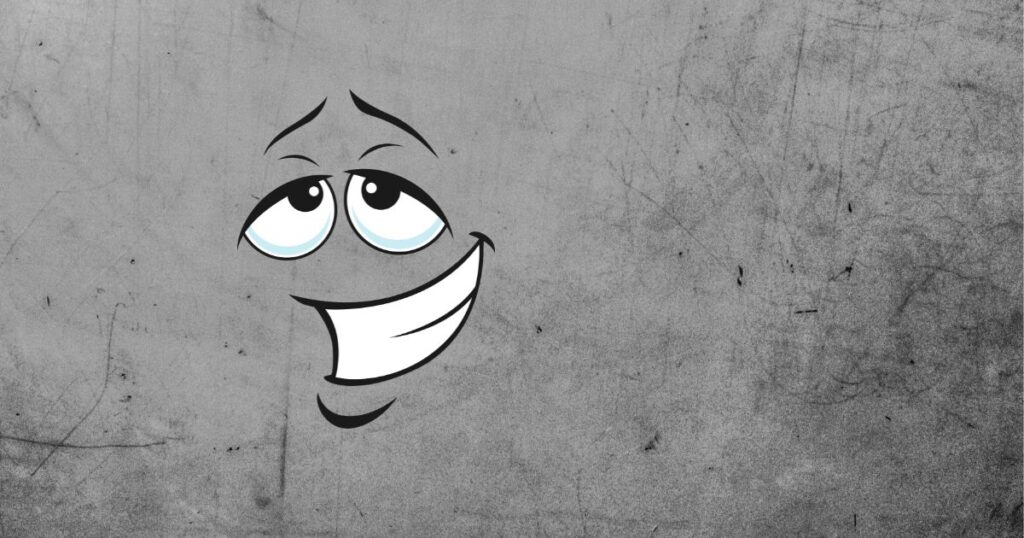
まとめ
目撃者の曖昧な証言、法医学者による冷静な分析、そして異文化のズレ──。
この日の法廷は、事件の表層だけでなく、社会の奥深い部分をも照らし出す一日となりました。
補足として
今回の目撃者に限らずこの社員寮での出来事は私にとって気持ちの悪い印象を与えました。
彼らは職場でも、社員寮においても問題なく「普通」に過ごせていると言っていますが、
この彼らのいう「普通」という概念が私たちの持つ「普通」と明らかに違うことです。




コメント