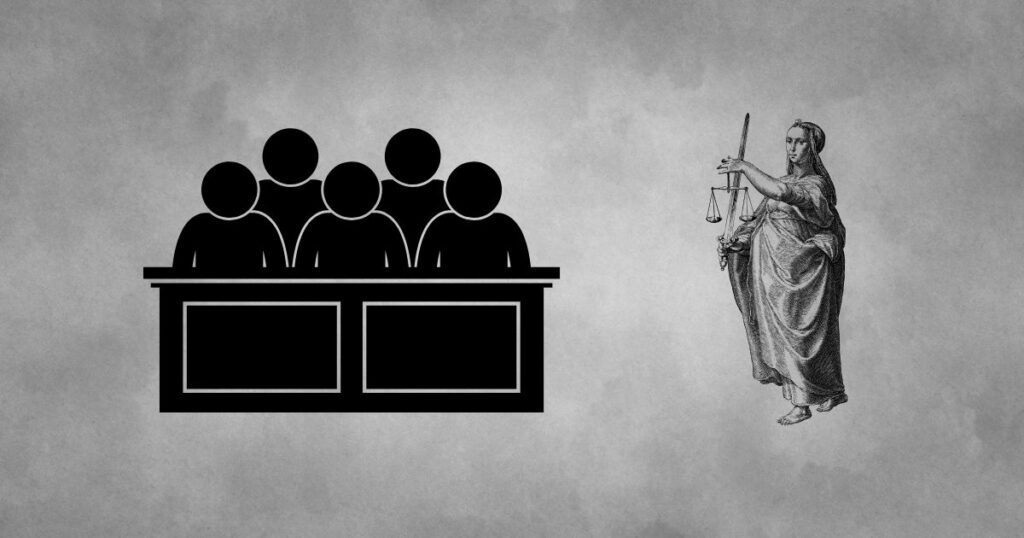
◆ 評議という名の「最後の議論」
法廷での論告・弁論・被告人の最終陳述を終えた翌日、我々裁判員は控室にて罪状を決める話し合い、いわゆる評議に入りました。
裁判官3名がそれぞれ役割を担い、我々の意見を引き出していく形で進行します。右陪席の判事が進行役、左陪席の判事が質問や資料の作成・提示を担当し、裁判長が全体をまとめる構成です。
私は今回、補充裁判員として参加しており、議論には自由に意見を出せる立場でしたが、最終的な評議権は持ちません。つまり、“意見は言えるが、票は入れられない”立場です。
最終判断は、裁判官3名と裁判員6名の多数決によって決まります。

◆ 弁護と検察、二つの視点を提示してみた
私は今回、あえて「嫌味なおっさん役」として、議論を深める提案をしてみました。
まずは弁護人の主張する「傷害罪」に情状を酌量する方向で意見を出し、次に検察官の提示する「殺人未遂」にも理解を示す立場から反対意見を述べてみる、という両面提示です。
しかし、被告人のこれまでの経緯――つまり過去の行動や証拠隠滅の意図などを踏まえると、情状酌量の余地はほとんどなく、最終的には「殺人未遂」の方向で意見がまとまっていきました。

◆ 日本の刑罰の「短さ」に感じた違和感
評議を通して感じたのは、日本の懲役刑が全体的に短いという点でした。
これは決して被害者感情を代弁するつもりではありませんが、他国の刑期や社会的制裁と比べても、どこか“軽く感じる”部分があります。
もっとも、これは感情論で測れるものではなく、過去の判例に基づいた法的均衡から導かれていることも、議論の中で理解できました。
それでもやはり、「法と感情のズレ」は、誰もが感じるテーマなのかもしれません。
◆ 司法と市民感情、その微妙な距離感
評議の場で思ったのは、司法が独り歩きしないためにこそ、市民の視点が必要だということでした。
どれだけ制度が整っていても、人間が裁く以上、そこには感情や倫理観が伴います。
裁判員制度という仕組みが存在するのは、まさにその“接点”を見つけ出すためなのかもしれません。

◆ 予定外の「自由時間」
今回の評議は、本来2日間を予定していました。
しかし意見がスムーズにまとまり、1日で結論が出てしまいました。
これにより翌日の予定がキャンセルされ、私のバイト日数がひとつ削られる結果に……。
心の中ではつい、「もう少しごねてみればよかったかな……」と苦笑い。
司法の場の重みを感じつつも、生活者としての現実が頭をよぎる――そんな1日でした。
※本記事は、実際の裁判員制度体験をもとに執筆したエッセイです。守秘義務に抵触しない範囲で記述しています。




コメント